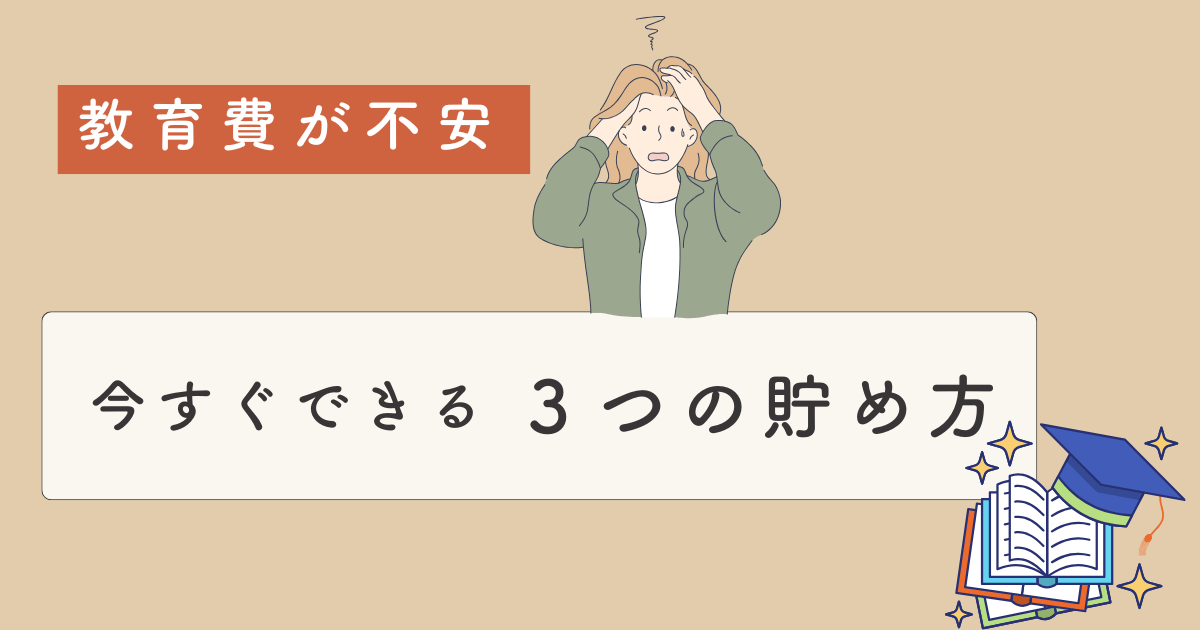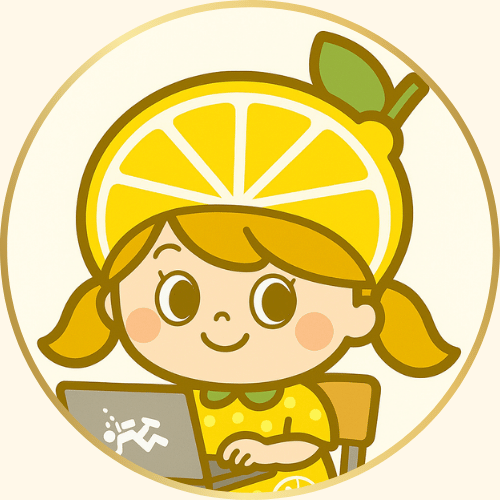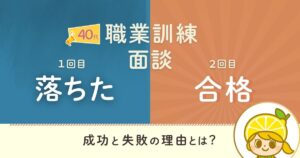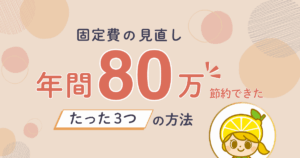「教育費、どう備えていますか?」
わが家では、2人の子ども(中1・小5)の将来に向けて、3つの方法でコツコツ積み立てています。
最近、ママ友と子供の進路についての話題が増えてきましたが、詳しいお金の話までは、なかなかできません。
 ゆるなつ
ゆるなつ教育費いくら貯める?現金?学資保険?何で備えればいい?
40代になると、自分たちの老後のことも気になりはじめる年齢。計画的に準備をしていないと、「教育費や老後資金」お金が足りない!という状況になってしまいます。



体験談を交えながら「教育費の3つの貯め方」を公開していくよ
わが家の教育費の備え方は、以下の「3つの方法」で備えています。
- 学資保険
- 現金貯金
- 投資(新NISAなど)
最近は、「投資」で備える人も増えていますが、「投資ってちょっと怖い…」という方も多いですよね。
そんな方にも安心して読めるよう、リスクを抑えた方法を中心にご紹介しています。
- わが家の3つの貯め方:【学資保険・新NISA・現金】金額を公開
- 貯めどきを逃す原因:わが家がやめたこと
- 教育費の目安は?:公立・私立・大学までに必要なお金
教育費はどう備える?


わが家では、「学資保険」「新NISA」「現金貯金」の3つを組み合わせて教育費を準備しています。
1. 学資保険でコツコツ積立
わが家では、子どもが生まれてすぐに学資保険に加入しました。
2人とも0歳のときに契約し、毎月1万円ずつ積立しています。
加入のきっかけは、両親から「子どもが生まれたら入るもの」とすすめられたこと。
当時は、お金の勉強をしていなかったので、学資保険=安心と思い、何も考えずに決めていました。
・親に万が一のことがあっても保証される
・元本保証がある(返戻率100%以上のもの)
・強制的に貯金できる
貯金だと使ってしまう、万が一の保証が欲しいという方は、選択肢に入れるのもありかなと思います。
でも、今なら「学資保険」は選ばない…
お金の勉強をした今の私なら、2人の学資保険には入らず「新NISA」で備えます。
新NISAとは…2024年から始まった「非課税で投資ができる制度」です。
詳しくは→金融庁の「新NISA特設サイト」をご覧ください
なぜ「新NISA」で備えるの?
- 自分で運用先を選べる
- 運用益が非課税で受取れる
- 将来の教育費を増やせる可能性がある
もちろん、どちらが正解というわけではなく、家庭の考え方や状況に合わせて選ぶことが大切です。
毎月いくら?3つの備え方と金額を公開
わが家では、3つの貯め方で2人分の教育費を準備しています。
月々の備えは…「児童手当と収入」から月7万円
- 学資保険:2万円 / 月
- 新NISA:5万円 / 月
年1回の備えで…ボーナスから年20万円
- 現金貯金:10万円✖️2人分=20万円 / 年



月々の負担がキツいと、結局続かないから…。現金の備えは、ボーナス時だけにしているよ。
1. 学資保険
加入した当時は、利率103%という条件だったこともあり、安心感を重視して加入しました。
現在も「貯金代わり」としてコツコツ続けています。
- 利率103%で、かけた分より少し多く戻るから
- 万が一のとき払込免除があるから
- 今さら解約しなくても、貯金代わりになるから
これからはじめるなら新NISAの方が効率的ですが、すでに契約しているものはそのまま活用していきます。
2. 新NISA
子どもが大学生になるまでに、「できるだけ効率よく教育費を準備したい!」
でも、銀行に預けているだけでは「お金はほとんど増えない…」と悩んでいました。
そんな中、お金のことをyoutubeや本などで少しずつ勉強するうちに、「投資は怖くない、知識があればお金に働いてもらえる」という考えに変わりました。
今では、新NISAを活用して効率よく教育費を積み立てています。
実際に新NISAで積み立ている状況はこちら⬇️(※教育費と老後資金を合わせた運用結果です)


積み立てた金額より約30% プラスになっています。
例)100万円積み立てた場合は約30万円増えてるイメージです
⚠️ 投資にはリスクがあり、運用成果を保証するものではありません。
3. 現金貯金
40代になると、教育費に加えて老後資金も気になりはじめる方も多いのではないでしょうか?
そこで、わが家では老後資金も月々貯めていきたい思い、「教育費の現金は毎月貯めない」という選択をしました。
毎月の収入と児童手当で「学資保険」と「新NISA」を活用していますが、正直、現金まで毎月貯めるのはむずかしい。
そこで、現金の備えはボーナス時にすることに。
教育費は、投資だけに頼らず、リスク分散のためにも現金を確保するようにしています。
ちなみに、わが家では楽天銀行を使って、スマホひとつで子どもたち名義の口座に教育費を貯金しています。



ネット銀行などを活用して、手間なく貯まる仕組みを作るのも大切なポイントです!
教育費にかかる金額とは
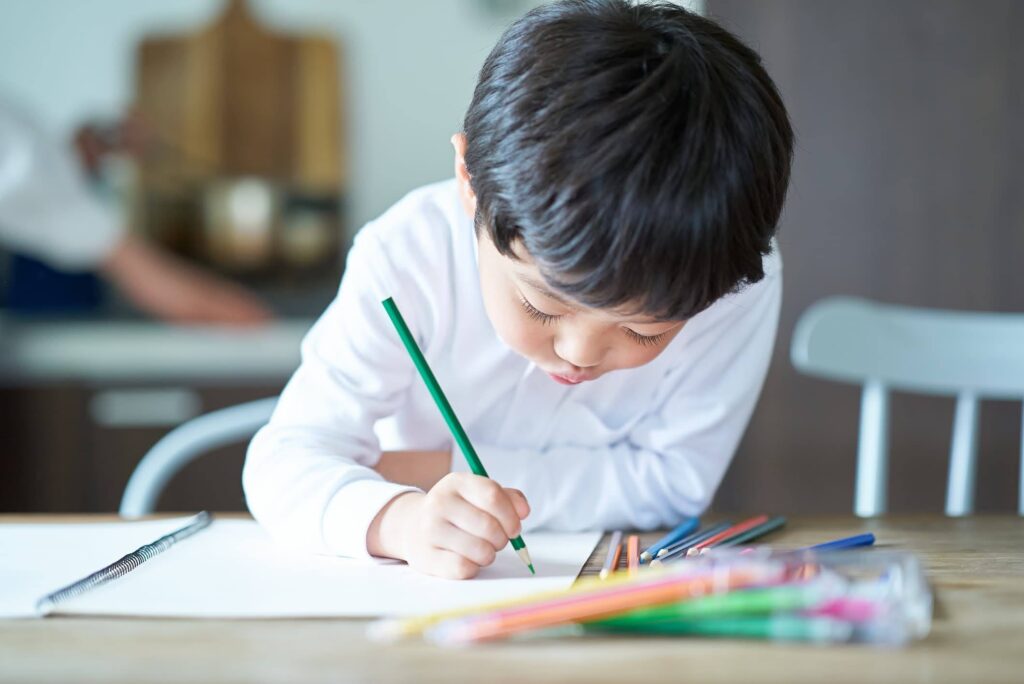
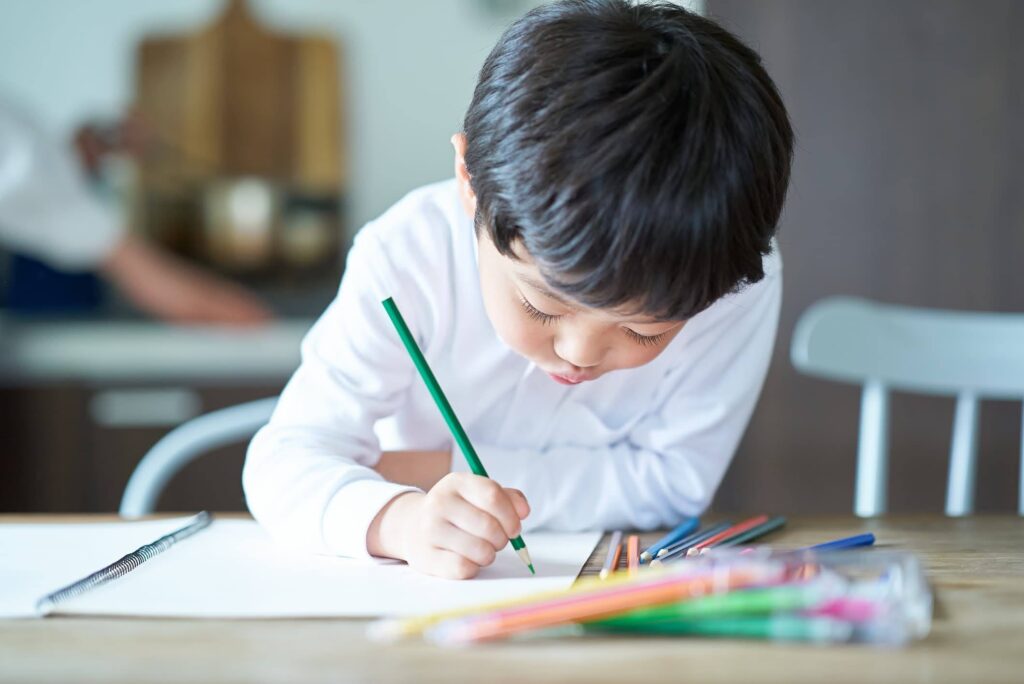
教育費は、子供の進路で大きく費用が変わります。
「幼稚園〜高校まで」と「大学」の教育費を文部科学省の資料をもとに以下にまとめました。
15年間でいくら必要?【幼稚園〜高校】
| 通学パターン | 総額(万円) | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | |
| ケース1 | 全て公立 | 約596万円 | 52万円 | 202万円 | 163万円 | 179万円 |
| ケース2 | 幼稚園(私立)、他は公立 | 約647万円 | 103万円 | 202万円 | 163万円 | 179万円 |
| ケース3 | 幼稚園・小学校(私立)、他は公立 | 約776万円 | 103万円 | 466万円 | 163万円 | 179万円 |
| ケース4 | 全て私立 | 約1976万円 | 103万円 | 466万円 | 306万円 | 467万円 |
*出典:文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」より計算
- ケース1 (すべて公立)の場合、約596万円( 3.3万円 / 月)
- ケース1 (すべて私立)の場合、約1969万円( 11万円 / 月)



公立と私立では、月々約7.7万円と大きく差があります!
どの進路を選ぶかで、必要な備えは大きく変わることがわかりますね。
大学費用はいくらかかる?
日本政策金融公庫の「令和3年度教育費負担調査」をもとに、比較した「入学費用と授業料」を以下にまとめました。
【入学時にかかるお金】
| 入学費用(平均) | |
| 国公立大学 | 約67.2万円 |
| 私立大学(文系) | 約81.8万円 |
| 私立大学(理系) | 約88.8万円 |
*出典:日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査」
入学金や施設費、教材費などが含まれます。
実際の負担は、準備品や引越し費用を含めると95万円〜145万円ほど必要になるケースもあります。
【在学中にかかる年間の授業料】
| 年間授業料(平均) | 月換算 | |
| 国公立大学 | 約53.3万円 | 約4.4万円 |
| 私立大学(文系) | 約86.2万円 | 約7.2万円 |
| 私立大学(理系) | 約107万円 | 約8.9万円 |
*出典:日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査」



他にも交通費や生活費、家から通わない場合の仕送り…って考えるといくら貯めても不安が残りそう。



だからこそ、計画的に準備することが大切だよ
教育費が貯まらない理由とその対策


「もっと貯めておけばよかった…」そんな声、実は先輩ママからよく聞きます。
わが家も、上の子が高学年になった頃から習い費が増えはじめました。
その後、下の子も高学年になり「あれもやりたい!これもやってみたい!」となり…
気がつけば、月5万円超え!さらに、イベントごとに費用がかかり負担が大きかったです。



子どもが「やりたい!」と言えばやらせてあげたい。
でも、一度はじめた習い事、やめるのって本当にむずかしいんですよね。
お金がきつくても、頑張る子どもの姿を見ると「もう少しだけ…」と先延ばしに。
でもその間に、「貯めどき」はどんどん過ぎていきます。
わが家は一時期、習い事の費用を負担に思っていたのですが、ある日「もう辞めたい」と子どもが言ってくれて、正直ホッとしました。
小学生の習い事にかける全国平均:月額16,676円(*出典:ベネッセ|子どもの習い事費用について)
中学生の習い事・学習費の全国平均:月額17,175円(*出典:家庭教師のランナー調べ)
費用だけでなく、地味にきつかったのが、送迎。
仕事終わりにおやつを用意して、学校まで迎えに行き、習い事に送り届ける。
そのあとは待機時間、帰宅後すぐに夕飯、お風呂…とバタバタ。
ワンオペの私には「時間と体力」も限界でクタクタな毎日でした。
「貯めどき」は逃さず、習い事は「目的と予算」を考えてはじめるのがポイント!
まとめ|これから教育費を貯めるなら


最近では、習い事の費用も年々上がり、子どもの教育費も上がり続けています。
「まだ、子どもが小さいし…」「余裕が出たら準備しよう」と後回しにしていると、気がつけば「貯めどき」はあっという間に過ぎてしまいます。
だからこそ、少しでも早く「貯まる仕組み」を作ることが大切。
以下の3つを意識して、行動することで未来は大きく変わります。
- 教育費は思った以上にかかる
「どれくらい必要か」知ることからスタート。 - 習い事は「目的」と「予算」で選ぶ
「みんなやってるから」ではなく、将来どんな力をつけたいか+予算のバランスで考える - 「貯めどき」は逃さず「貯まる仕組み」を作る
「先取り貯金」や「新NISA」で自動で貯まる仕組みを作れば継続しやすい
まずは、「わが家の必要な金額」を調べてみるのがおすすめです。
私もつかっている「新NISAでの仕組みづくり」については、こちらの記事で詳しくまとめています↓